糖鎖の持つ意味や重要性について
糖鎖とは化学的には単糖が結合して鎖のように長くなったものを指します。
単純に1本の鎖のように長くなる場合もありますし、途中で枝分かれが生じて分岐鎖を生じるものもあります。
身近なところでは、お米やパンなどに含まれるデンプン、植物の細胞壁の主成分であるセルロースなどがあります。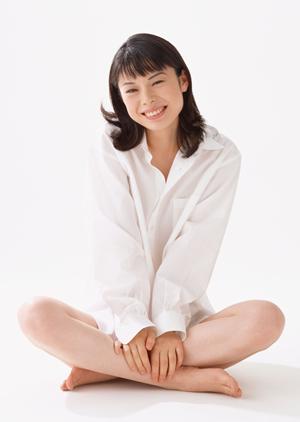
従来の生化学においては、これらは消化酵素によって単糖にまで分解されて吸収され、最終的にはエネルギー源として利用されるか、あるいはそもそも消化酵素によって分解されることなく食物繊維としての働きくらいしかないといった程度に捉えられることが多かったのです。
エネルギー源になるかそれともあまり役立たないかのどちらかに過ぎないというわけです。
これは、エネルギー源にもなるけれども、ヒトの体内で例えば筋肉になったり酵素を作ったりするために必要なタンパク質や、細胞膜の構成成分である脂質に比べると扱いが一段下というか、あまり機能的な役割を果たしていないと思われることも多かったわけです。
ですが、医学的な研究が進むにつれ、今では決してそんな単純なものではないと分かってきています。
体内において糖は単にエネルギー源になるだけの役割しかないわけではなく、いろいろな細胞に実はそれ特有の糖鎖が結合しており、それがあるからこそその細胞が正常に働いている、つまりは糖鎖というものはヒトの体が正常に働くために必須のものらしいということが次第に分かってきたのです。